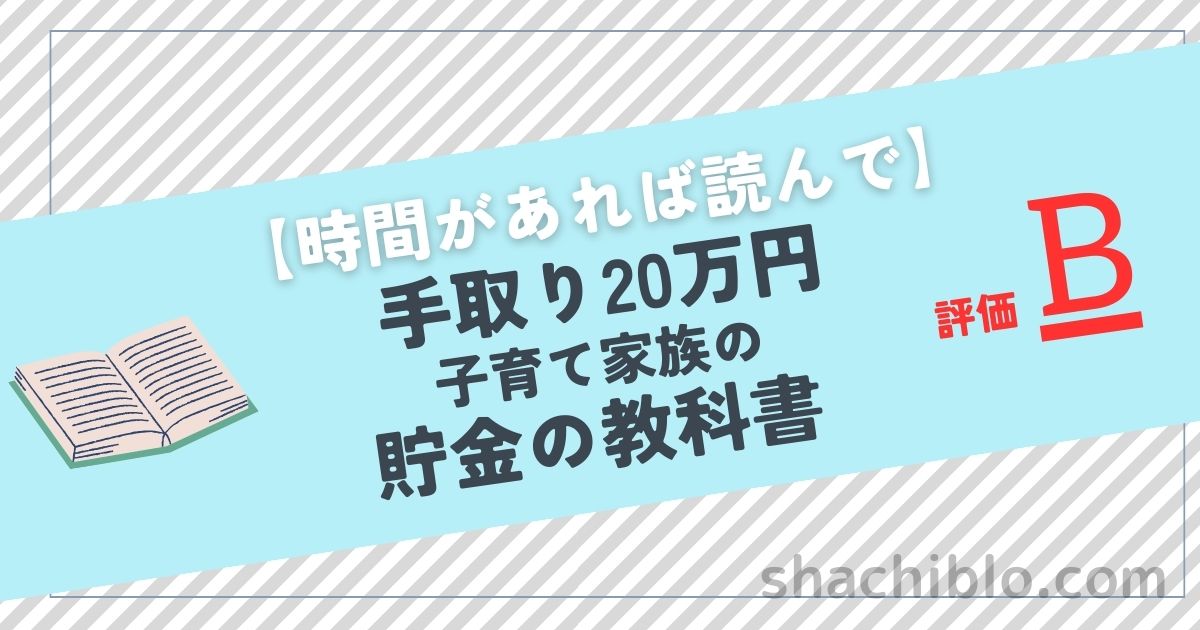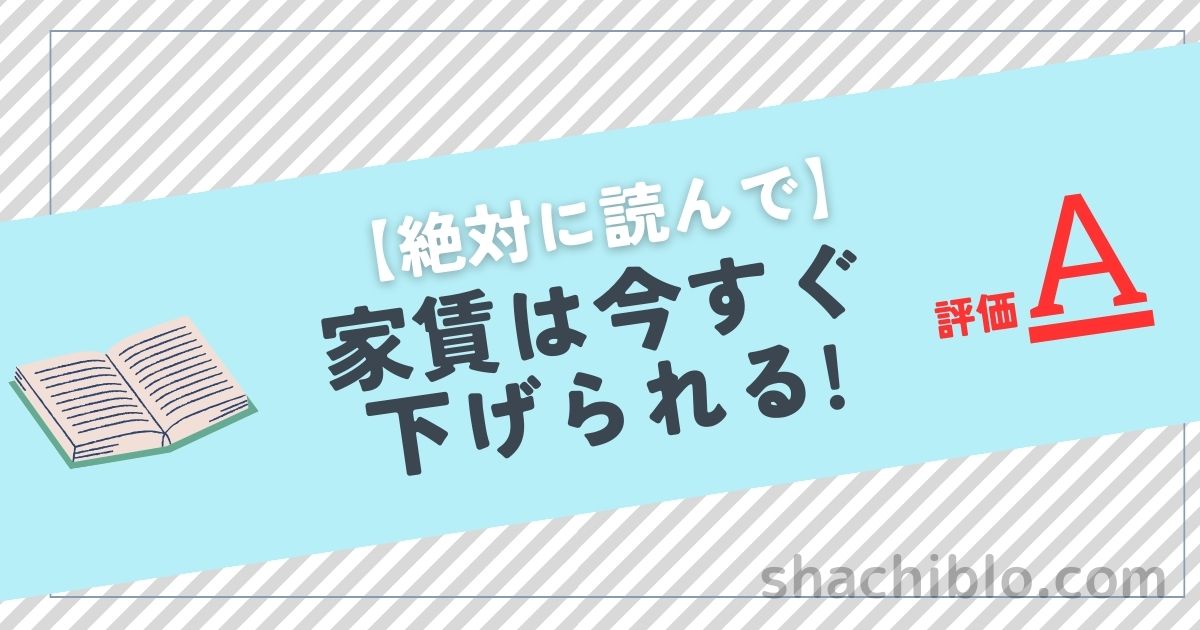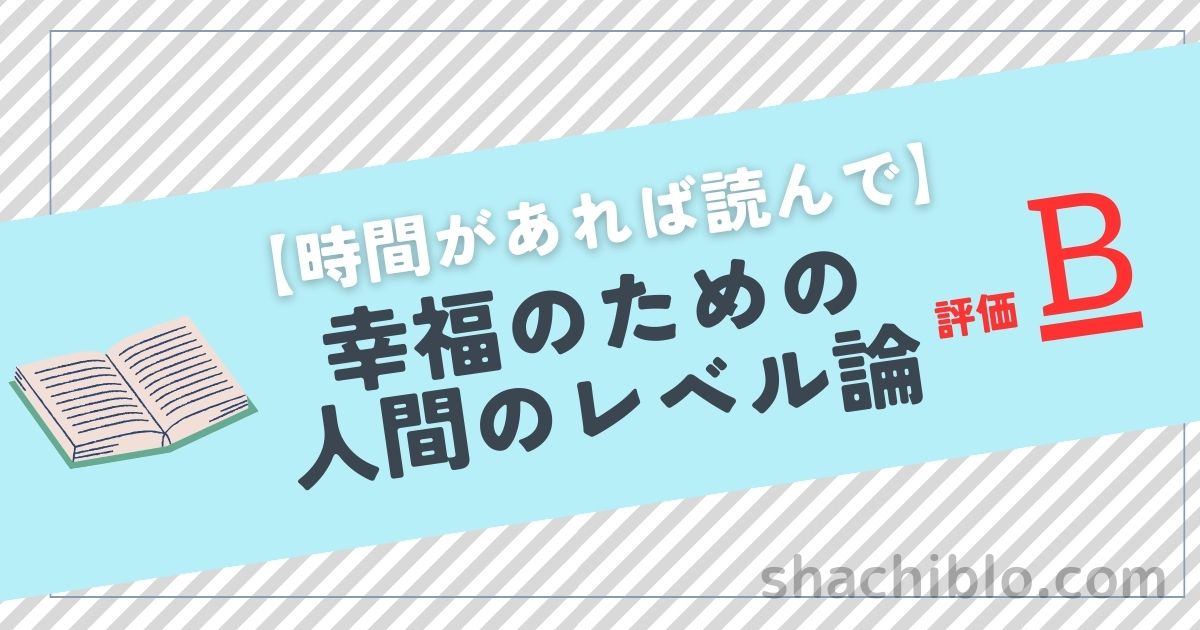この本は「貯金術を学ぶ本」ではなく、「子供にお金の知識を身に着けさせるためにどうすればよいかを学ぶ本」と思った方がしっくりくると思います。
子育て世帯は時間がある時に読んで欲しい一冊です。
一方で、子育てをしていない、する予定のない人は強いて読まなくてもよいでしょう。

著者プロフィール
・書籍名:手取り20万円 子育て家族の貯金の教科書
・著者:横山 光昭 / 朝倉 真弓
・出版月:2018/5/2
・出版社:きこ書房
<横山 光昭>
1971年、北海道生まれ。
家計専門に活動をはじめ、支出を「消・浪・投」に分ける「家計の三分法」を用いた独自の家計管理プログラムと、誰でもできる「ほったらかし投資」を両輪に、相談者に豊かな今と老後の生活を手に入れてもらうことを目指している。
家計相談はこれまでに2万6千件を超える。
<朝倉 真弓>
アパレル会社、出版社、編集プロダクションを経て、1999年にフリーランスライターとして独立。
インタビュアー・ライターとして3000人以上のインタビューと執筆を経験。
実用書やビジネス書の分野では企画やライティングを数多く務め、ストーリー仕立てのビジネス書(ビジネスストーリー)を得意とする。
本の目次
はじめに 子供の将来はお金の《使い方》で変わる
プロローグ 教育費1000万円のリアル
・月の手取り20万円で子育てはムリ?
・教育費の《リアルな出費》は・・・・・・
・教育費は《2つ》に分けて考えよう
・キツいのはやっぱり大学のお金だけど
第一章 大学入学までに300万円を貯める方法
・児童手当の賢い使い方
・児童手当をついつい使ってしまう理由
・子ども名義の通帳は絶対必要
・祖父母の援助に要注意
・教育資金作りに無理な投資は必要なし
・大学の残りの学費はどうする?
・夫婦と子ども二人、理想的な支出割合はこれ!
・貯蓄困難期はムリしなくてもOK
・ボーナスで家計安全度がわかる!
・たまにはレジャーに思い切って使う
・親のお小遣いはカットしてはいけない
【第二章】 学資保険はいらない
・いまの時代「保険で貯金」はうまみがない、
・学資保険に入っていいのはこんな人
・どうしても学資保険を選ぶなら・・・・・・
・貯蓄性に優れている保険はほぼない
・奨学金は絶対使っちゃダメ?
・奨学金を利用しても自力の300万円は必要
【第三章】 ここぞで使う貯金と保険
・貯金のための《2つの袋》
・《使わない貯金》は生活防衛費
・貯金は三角、保険は四角
・保険は「入る」のではなく《買う》もの
・遺族年金がいくらもらえるか、知ってますか?
・収入保障を検討しよう
・医療保険に入ったほうがいい人、入らなくていい人
・三大疾病の医療費はバカにならない
・入院日額はいくらあれば十分か?
・保険選びの《たった2つ》の基準
・子どもと専業主婦(夫)の保険は・・・・
【第四章】習い事のお金をムダにしない秘訣
・熟や習い事に毎月2~3万円?!
・ほとんどの家庭は習い事をさせすぎ
・習い事の費用をムダにしない方法
・子どもが「やりたい!」と言ったら?
・子どもに「いくらかかっているか」を伝える
・マイホームを買うタイミング
・持ち家は老後のために買うという考え方おわりに
【第五章】お金に強い子どもの育て方
・横山家の月イチマネー会議
・大事なのは金銭感覚)教育
・子どものお小遣いをちょっと多めに渡す理由
・お金の《小さな失敗》をさせておく
・スマホの明細は、必ず子どもに見せる
・高校生にはデビットカードを持たせてみる
・ネットのプリペイドカードもお金の管理に便利
【エピローグ】子育ては《老後》を見据えて
・教育資金と老後資金はシーソーの関係
・老後の生活費は年金でまかなえる?
・大事なのは《かけてあげられる額》
総合評価
S 人生が変わる神本
A 絶対に読んで
B 時間があれば読んで
C 強いて読まなくてもいい
D 時間の無駄
S 人生が変わる神本
A 絶対に読んで
B 時間があれば読んで
C 強いて読まなくてもいい
D 時間の無駄
序盤は教育費に関する内容です。
教育費は、高校卒業までに500~800万円かかり、大学まで含めると1,000万円近くかかりますが、一度にこの金額が必要になるわけではありません。
入学費などの突発的にかかるイニシャルコストと、定期的にかかるランニングコストを分けて考える必要があり、大学入学までに300万円貯めておけば何とかなることが述べられています。
児童手当の総額は198万円(2024年10月から高校生までもらえるようになったため、現在は234万円)であることを考えると、児童手当をすべて貯蓄したうえで、さらに約70万円を大学入学までに貯めておけばよい計算になります。
冷静に金額を把握することで、金銭面の不安がぐっと小さくなるはずです。
また、子育て世帯が貯蓄する際の注意点についても述べられており、特に保険について詳しく説明されています。
保険は保険、学資は学資で分けて考えたほうがよく、学資保険は不要であることや、医療保険に入ったほうがよい人の条件などが解説されています。
「保険は入るものではなく買うもの」「貯金は三角、保険は四角」など、印象に残るワードがあり、勉強になります。
ここまでは知っている内容も多かったですが、最も参考になったのは、子どもをお金に強くするために、どのような金銭教育をすればよいかについてです。
例えば、月に一回子どもを交えて、一か月でかかった生活費を共有するマネー会議を開いたり、習い事の費用を子どもにもきちんと伝えるといった方法です。
賢いお金の使い方を身につけておくことは、人生の武器になります。
子どもにお金の失敗をしてほしくない親には、ぜひ読んでほしい一冊です。
一方で、子育てをしていない、またはする予定のない人は、強いて読まなくてもよいと思います。
貯金のゴール設定や貯金方法が子育て世代を対象としたものだからです(児童手当を考慮するなど)。
個別評価(育児本として)
新規性 ー 新しい情報があるか
今までに見たことがなく、人生を変える価値観を学べる
今までに見たことがないアイデア、見方を数多く学べる
今までに見たことがないアイデアがいくつかある
今までに見たことがない情報がいくつかあるが、役には立つものは少ない
目新しい情報はほとんどない
メインテーマである貯金の方法については、すでにマネー本を読んでいる人にとって新しい情報は少ないでしょう。
教育費や保険のかけ方などを再確認する程度の内容です。
しかし、新規性があるのは後半に書かれている「習い事のお金をムダにしない秘訣」「お金に強い子どもの育て方」です。
特に、小学生以上になり、お金の価値をだんだんと理解し始めた子どもを持つ親に読んでほしい内容となっています。
汎用性 ー 多くの人の役に立つか
すべての人の役に立つ
多くの人の役に立つ
ある対象の人に対して役に立つ
僅かだが役に立つ人がいる
ほぼ誰の役にも立たない
すべての子育て世代にとって有益な本です。
お金の貯め方だけでなく、子どもへのお金の教育をどのようにすればよいかを学ぶことができます。
わかりやすさ ー 理解しやすい工夫があるか
パッと見て内容を深く理解できる
普通に読めば内容を理解できる
集中して読めば内容を理解できる
何回も読まなければ内容を理解できない
意味不明
手取り20万円のサラリーマンである男性と、FP(ファイナンシャルプランナー)である筆者の対話形式で書かれており、非常に読みやすいです。
ページ数も207ページとコンパクトで、1時間もあればサラッと読むことができます。
実用性 ー 本を読んですぐに役に立つか
読んで即座に実行できるアイデアが数多くある
読んで即座に実行できるアイデアがいくつかある
即座に実行できるアイデアはないが、長期的にみれば役に立つ
確率は小さいが、人生のどこかで役に立つかもしれない
役に立たない
貯金するための基本的な考え方を学ぶことができ、
不要な保険に加入している人は解約などの具体的なアクションにつなげることができます。
また、子どもへの金融教育の方法が具体的に書かれているため、そのまま実践することが可能です。
個別評価(資産形成・経済本として)
新規性 ー 新しい情報があるか
今までに見たことがなく、人生を変える価値観を学べる
今までに見たことがないアイデア、見方を数多く学べる
今までに見たことがないアイデアがいくつかある
今までに見たことがない情報がいくつかあるが、役には立つものは少ない
目新しい情報はほとんどない
メインテーマである貯金の方法については、すでにマネー本を読んでいる人にとって新しい情報はあまりありません。
汎用性 ー 多くの人の役に立つか
すべての人の役に立つ
多くの人の役に立つ
ある対象の人に対して役に立つ
僅かだが役に立つ人がいる
ほぼ誰の役にも立たない
対象は子育て世代に限定されます。
独身世帯や子どもを持つ予定のない夫婦は、特に読む必要はありません。
わかりやすさ ー 理解しやすい工夫があるか
パッと見て内容を深く理解できる
普通に読めば内容を理解できる
集中して読めば内容を理解できる
何回も読まなければ内容を理解できない
意味不明
手取り20万円のサラリーマンである男性と、FP(ファイナンシャルプランナー)である筆者の対話形式となっており、非常に読みやすいです。
ページ数も207ページとコンパクトで、1時間もあればサラッと読むことができます。
実用性 ー 本を読んですぐに役に立つか
読んで即座に実行できるアイデアが数多くある
読んで即座に実行できるアイデアがいくつかある
即座に実行できるアイデアはないが、長期的にみれば役に立つ
確率は小さいが、人生のどこかで役に立つかもしれない
役に立たない
貯金するための基本的な考え方を学ぶことができますが、子育て世帯を対象とした戦略がメインのため、独身世帯や子どもを持つ予定のない夫婦にとっては学ぶ点が少ないでしょう。
印象に残ったポイント
貯金は三角、保険は四角
貯金は、時間軸が増えていくにしたがって積み重なり、額が増えていく。
一方で保険は、契約した直後から、万が一の場合に大きな保障を得ることが出来る。
保険は入るものではなく買うもの
一家の働き手に何かあったときに、家族が路頭に迷わないように、必要な保障の部分だけを、掛け捨ての保険で《買う》。
保険に長く入って、貯蓄もかねて、という考えは非効率。
掛け捨てにすれば、毎月の保険料を少なくして、大きな保障を取ることが出来る。
医療保険に入るべき人
高額療養費制度が使えない、差額ベッド代や、先進医療に備えるために、300万円を医療費として別に用意できる人以外は、医療保険に入るべきだと本書では述べられている。

この意見に関しては、私は否定的です。
そもそも先進医療は、効果が未知数のものであり、積極的に利用する必要はないと思います。
(健康保険が適用される医療法は、効果が十分に確認されている最高のものです。)
また、保険は確率が小さいが、当たると損失が大きいものに備えるものであり、医療保険はリーズナブルとは言えません。
唯一、この部分はうのみにしてはいけないと思いました。
習い事のお金をムダにしない秘訣
習い事のお金をムダにしない秘訣は「やめどきを見逃さないこと」。
子供本人はたいして好きでもないし、やる気も無いのに、惰性や親の願望だけで習わせるのは、子供のストレスにもなるし、お金の無駄。
3か月に1回くらいのペースで子供に話を聞き、子供のやる気を確認するのが大事。
また、習い事や塾に、「いくらかかっているか」を子供に伝えることも重要。
子供が自然と真剣になり、また限られた予算で何を選ぶかを自分で考えるようになる。
まとめ
この本が気になる人は、お金に関心のある親だと思います。
そんな親は、子供にもお金で失敗しない知識を身に着けて欲しいと思っているはずです。
この本は貯金術を学ぶ本ではなく、子供にお金の知識を身に着けるためにどのようにすればよいかを学ぶ本だと思った方が、しっくりくると思います。
子育て世帯にとっては、時間がある時に読んでおくとプラスになる本です。

最後まで読んでいただきありがとうございました!
にほんブログ村
応援クリックいただけると励みになります!