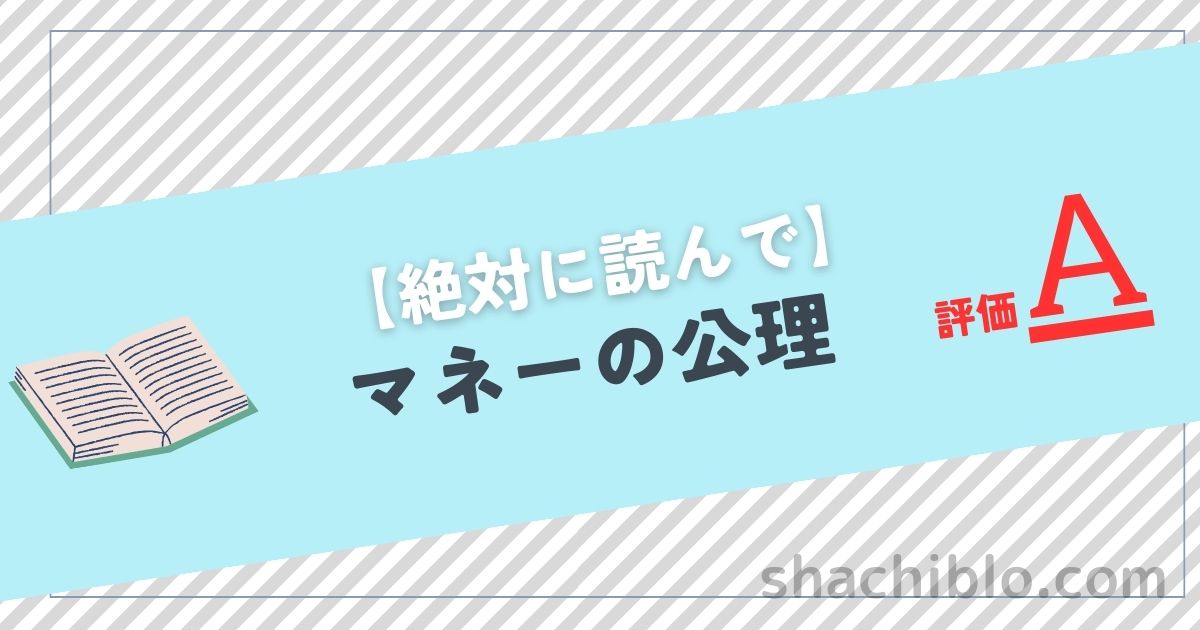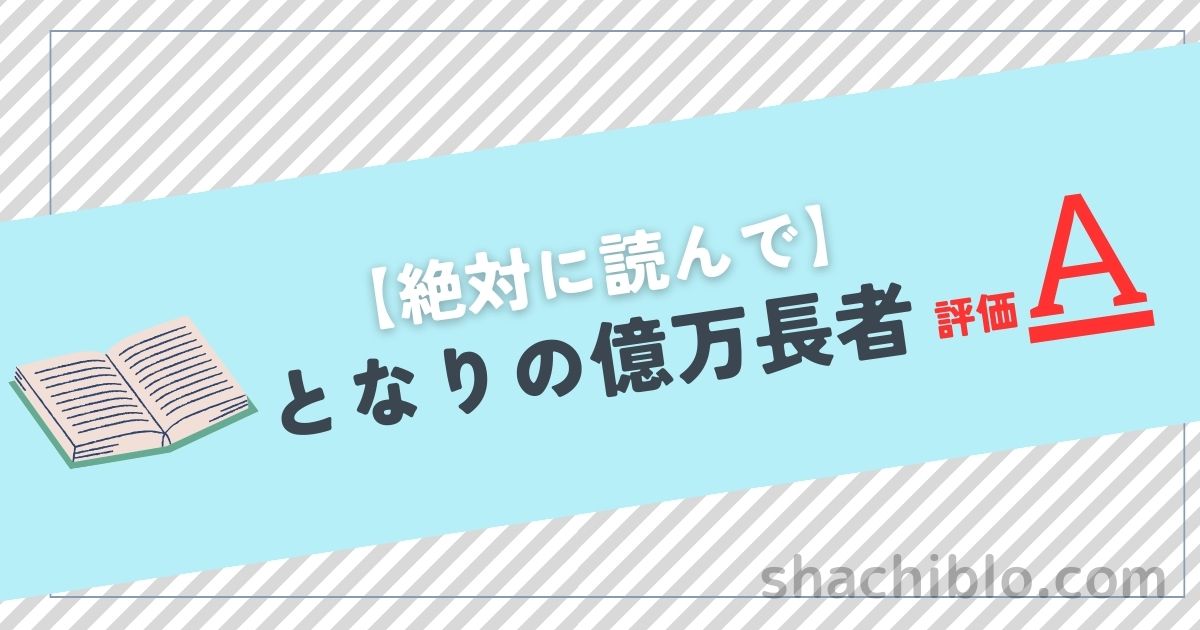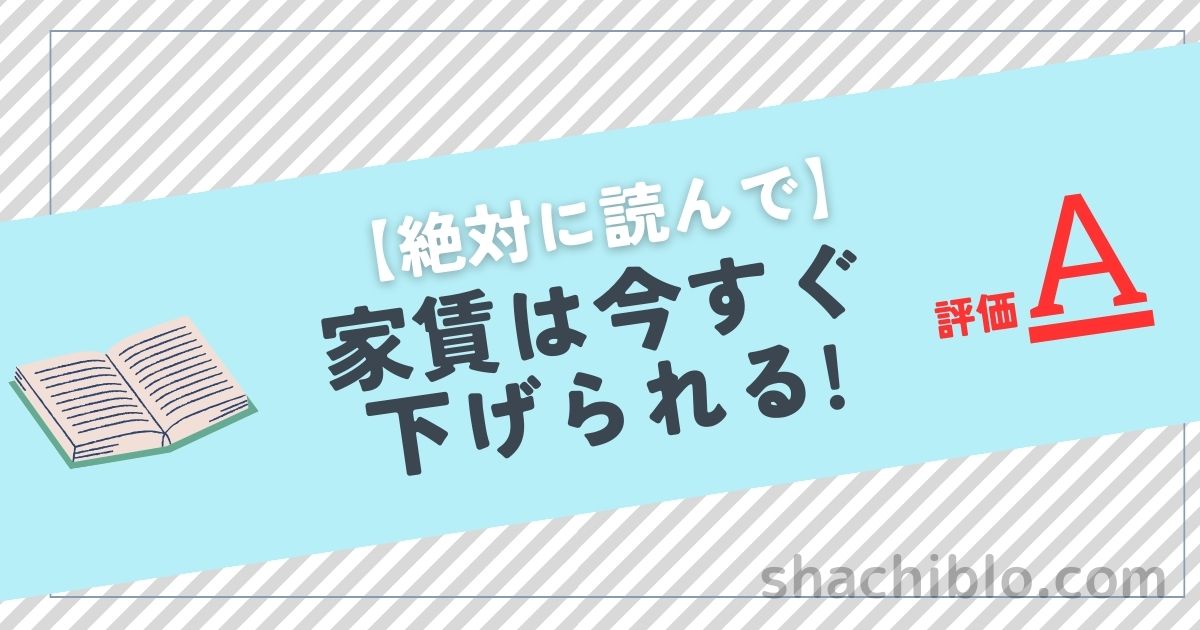投機に関する本として紹介されることも多いですが、もっと広い意味での「賭け」や「選択」をどのように行えばよいかという哲学を学べる良著です。
すべての人に絶対に読んでほしい一冊です。

著者プロフィール
・書籍名:マネーの公理
・著者:マックス・ギュンター
・出版月:2005/12/22
・出版社:日経BP
英国生まれの作家、ジャーナリスト、投資家。11歳で米国に移住。
プリンストン大学卒業後、『ビジネスウィーク』誌勤務を経て、『プレイボーイ』『リーダーズ・ダイジェスト』『サタデー・イーブ二ング・ポスト』などの雑誌、新聞に寄稿するようになる。
父親はスイス銀行界で活躍した人物で、世界的に名を知られた「チューリッヒの小鬼たち」と呼ばれたうちの一人。
自らも13歳で株式マーケットに参入し、財を成す。
本の目次
はじめに 公理とは何か、どこからきたのか
第一の公理 リスクについて ー 心配は病気ではなく健康の証である。もし心配なことがないなら、十分なリスクをとっていないということだ
第二の公理 強欲について ー 常に早すぎるほど利食え
第三の公理 希望について ー 船が沈み始めたら祈るな。飛び込め
第四の公理 予測について ー 人間の行動は予測できない。誰であれ、未来がわかると言う人を、たとえわずかでも信じてはいけない
第五の公理 パターンについて ー カオスは、それが整然と見え始めない限り危険ではない
第六の公理 機動力について ー 根を下ろしてはいけない。それは動きを遅らせる
第七の公理 直観について ー 直観は説明できるのであれば信頼できる
第八の公理 宗教とオカルトについて ー 宇宙に関する神の計画には、あなたを金持ちにすることは含まれていないようだ
第九の公理 楽観と悲観について ー 楽観主義に居場所を知っていることを意味し、自信は最悪に対処する術を知っていることを意味する。楽観のみで行動してはならない
第十の公理 コンセンサスについて ー 大多数の意見は無視しろ。それはおそらく間違っている
第十一の公理 執着について ー もし最初にうまくいかなければ、忘れろ
第十二の公理 計画について ー 長期計画は、将来を理解できるという危険な確信を引き起こす。決して重きを置かないことが重要だ
総合評価
S 人生が変わる神本
A 絶対に読んで
B 時間があれば読んで
C 強いて読まなくてもいい
D 時間の無駄
スイスは国土が狭く、資源も乏しい国です。
そんなスイスが発展してきたのは、スイス人が投資家、投機家、ギャンブラーとして成功してきたからです。
そして、スイス人が特性として持っている「合理的にリスクをとる力」を言語化し、具体的に解説したのが本書です。
「合理的にリスクをとる力」は、12個の公理と16個の副公理としてまとめられており、そのどれにも重みを感じます。
“監訳者あとがき”にも書かれていますが、本書の優れている点はとにかく具体的であることです。
たとえば、「第七の公理 直感について」では、「直感は説明できるのであれば信頼できる」とされています。
普通の本であれば、誰かのエピソードを紹介して説得力をつけるだけで説明が終わりそうなものですが、本書では、直感を感じた際にどのように行動すればよいのかが書かれています。
具体的には、その直感を生み出すほどの巨大なデータの図書館が自分の心の中に存在するかを自問し、その答えが「YES」なら直感を信じてもよいとしています。
このように、それぞれの公理それぞれに、具体的な指針やアプローチがしっかりと書かれています。
一方で、「分散投資はダメ」「長期投資はダメ」など、多くの人にとって参考にしづらい部分もあります。
投機に関する本として紹介される理由は、このあたりにあるのかもしれません。
すべての内容を妄信できないことには注意する必要があります。
本書は「賭け」に関する本であると同時に、「人生」についての本でもあります。
なぜなら、人生は選択の連続であり、それは賭けの連続ともいえるからです。
日々の生活の中で選択に迷ったときの指針となる一冊であり、羅針盤として手元に置いておきたい本です。
個別評価
新規性 ー 新しい情報があるか
今までに見たことがなく、人生を変える価値観を学べる
今までに見たことがないアイデア、見方を数多く学べる
今までに見たことがないアイデアがいくつかある
今までに見たことがない情報がいくつかあるが、役には立つものは少ない
目新しい情報はほとんどない
賭けをするうえでの指針を、綺麗かつ具体的にまとめている点が新鮮です。
それぞれの公理も、多くの新しい発見をもたらしてくれます。
汎用性 ー 多くの人の役に立つか
すべての人の役に立つ
多くの人の役に立つ
ある対象の人に対して役に立つ
僅かだが役に立つ人がいる
ほぼ誰の役にも立たない
人生はすべてギャンブルであるため、本書が伝える内容はすべての人にとって役立ちます。
わかりやすさ ー 理解しやすい工夫があるか
パッと見て内容を深く理解できる
普通に読めば内容を理解できる
集中して読めば内容を理解できる
何回も読まなければ内容を理解できない
意味不明
全253ページとコンパクトな一冊です。
イラストなどはありませんが、12個の公理と16個の副公理が整然と説明されており、非常にわかりやすいです。
実用性 ー 本を読んですぐに役に立つか
読んで即座に実行できるアイデアが数多くある
読んで即座に実行できるアイデアがいくつかある
即座に実行できるアイデアはないが、長期的にみれば役に立つ
確率は小さいが、人生のどこかで役に立つかもしれない
役に立たない
人生の羅針盤となる内容が書かれています。
即座に実行できるアイデアは多くありませんが、長い目で見れば非常に有用な本です。
印象に残ったポイント
・第二の公理 強欲について ー 常に早すぎるほど利食え
ブームがピークに達するのを待ってはいけない。
勝利は続かないと考えなければならない。
あらかじめ決めておいたゴールに達したら手仕舞って立ち去る必要がある。

『ユダヤ人の成功哲学「タルムード」金言集』でも、ローリスク・ローリターンを繰り返すことが大事だという内容がありました。
成功哲学は普遍的ですね。
第五の公理 パターンについて ー カオスは、それが整然と見え始めない限り危険ではない
お金の世界にはパターンがなく、無秩序で混沌としている。
このカオスの中で公式を見つけようとしてはいけない。
この公理は、有利な賭けや見込みのある投資を見つける望みを捨てるべきだと言っているわけではない。
調査や研究で勝算が高まっても、運こそが投機の成功や失敗において最も強力な要因であることを忘れてはいけないことを説いている。
もしも自らの選択で間違いが起こったときにすぐに対応できるようにする必要がある。
第八の公理 宗教とオカルトについてー宇宙に関する神の計画には、あなたを金持ちにすることは含まれていないようだ
占星術が当たるのであれば、全ての占星術師は金持ちだろう。
だが、占星術師が一般人よりも金持ちという事実はない。
お金を賭けているときに頼れるのは自分1人だと覚悟しなければならない。
一方で、楽しんで使うのであれば迷信を追い払う必要はない。
例えば、ロトなどの運の要素しかないゲームで、迷信や占星術をもとに数字を決めてもよいだろう。
大事なときに迷信に頼らなければ、人生を楽しめるかもしれない。
まとめ
非常に薄い本でありながら、内容が非常に濃い一冊です。
ぜひ手元に置き、人生のさまざまな選択の際に羅針盤として活用してほしいです。

最後まで読んでいただきありがとうございました!
にほんブログ村
応援クリックいただけると励みになります!